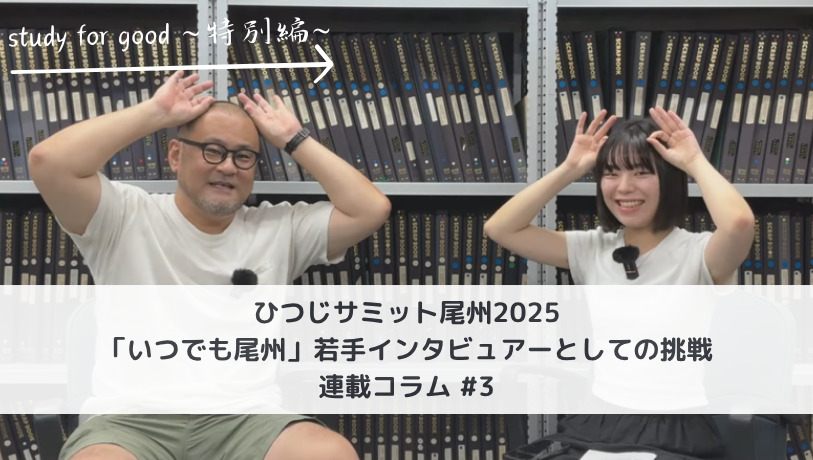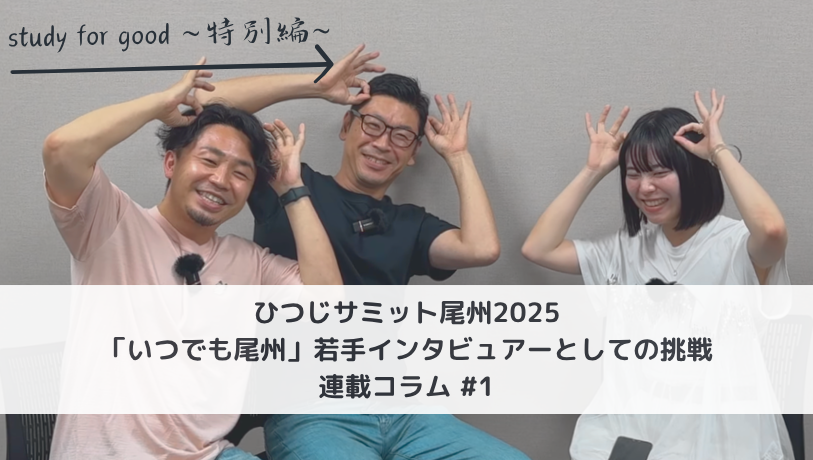サステナブル、エシカルといった領域やそれに関心を持つ業界人・消費者が気になるキーワード・概念を軸に、「分からないことを分からないなりに考える」ための思考の道筋を共有するコラムシリーズ「サステナブルの補助線」。前回は「リジェネラティブを整理する」の初回として、サステナブルの発展形に止まらないリジェネラティブの在り方に触れました。
今回は、そんなリジェネラティブについて、特に「ホリスティック」というキーワードを軸に深掘りしていきます。
目次
- ホリスティックとは?
- ホリスティックとリジェネラティブ
- 最後にー「自然と人間」という図式
ホリスティックとは?
ホリスティックの語源はギリシャ語で「全体」「完全」を意味する「ホロス(holos)」。ホリスティックは「全体論的」などと訳され、部分ではなく全体を捉え、相互に関連する要素間のつながりを重視する考え方と説明されることが一般的です。物事をそれ単独ではなく、その文脈や周囲との関係性の中で捉え、全体最適を目指します。
たとえば、体の不調を例に考えてみましょう。西洋医学では症状が出ている部分に焦点を当て、その部分を治療する傾向があります。しかし、ホリスティックな視点では、身体は複雑に相互作用するシステムであり、一部分の不調は他の部分、さらには精神状態や生活習慣、社会環境との関わりからも影響を受けていると考えます。
ビジネスの世界でも、マーケティング活動の全てを統合的に捉え、顧客、従業員、取引先、株主、地域社会など、企業に関わる全てのステークホルダーとの長期的な関係構築を目指す「ホリスティックマーケティング」というマーケティング戦略があります。
これらの例に見られるように、個別の要素に分解して分析、改善を目指す専門性重視の要素還元的アプローチとは真逆の、現象全体をそのまま捉え、バランスや相互作用を重視する価値観がホリスティックの特徴と言えるでしょう。
ホリスティックとリジェネラティブ
ここでいったんリジェネラティブに立ち返ってみると、リジェネラティブがとても「ホリスティックな」ものであることが明らかになってきます。
複数の作物を共に植える間作や年ごとに異なる作物を栽培する輪作により作物を虫害などから守り土壌の健康性を保つ、農業コミュニティ内で有機肥料をつくることでそれに関わる女性たちの社会進出を助ける…こういったプラティバシンテックス社の取り組みは、個別のイシューに対応する独立した施策ではなく、それぞれが有機的に絡み合い全体の発展につながっている、非常にホリスティックなアプローチです。
今思えば、リジェネラティブを当事者として進める彼らの語りからは、「サステナブル」なことをやっているという主張や強い「気負い」を感じませんでした。先日のウェビナーを改めて見直すと、そこには農業も、土壌も、経済も、女性のエンパワメントも、全て個別の問題と扱わず相互関連を見据えた上で全体最適を「あたりまえ」に目指す彼らのホリスティックな価値観を感じ取ることができるような気がします。
このように「ホリスティック」を軸にリジェネラティブを整理すると、さまざまな要素が影響する「相互依存性」への眼差し、システム思考的な考え方が重要な要素として立ち上がってきます。
リジェネラティブなシステムは、自然の生態系のように、さまざまな要素が相互に依存し合い、全体としてのバランスを保っています。「⚪︎⚪︎を減らす」といった個別のエコ訴求とは大きく異なり、この全体の有機的なつながりこそが「リジェネ的」な価値といえます。
「サステナブル」において大事な価値である生物多様性や資源の循環はリジェネラティブにおいても大切にされますが、これらは多様な生物が相互作用することで生態系の安定性が維持される、廃棄物を最小限に抑え資源を循環させることで全体のバランスが整っていくという意味で全体最適につながるホリスティックな価値を持っています。
最後にー「自然と人間」という図式
ここまで考えてきて、リジェネラティブにはこのような全体を一つの「系」と捉えるホリスティックな世界観が存在するのでは・・・ということがおぼろげながら見えてきました。
相互に関連し影響を与え合うのなら、私たち作り手は、消費者は、さらにはそれらを含む人間一般は、その「系」に対してどこに位置するのでしょうか。
次回はリジェネラティブをより深く考えるために、西洋近代的サステナブルと東洋的リジェネラティブそれぞれの「自然」の捉え方や「自然と人間」の関係性についてさらに思索を進めます。
プロフィール

執筆
森 康智(もり やすとも)
採用プロジェクトチーム兼広報・IRチーム。2014年に東京大学大学院修了後、新卒でタキヒヨーに入社。新卒採用、キャリアコンサルティングやPRの専門知識を生かし、多様な人々の「問いと語り」によるシナジー創出を目指す。_ for goodのファシリテーター。